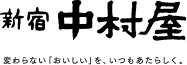木下尚江きのした なおえ
自由民権への憧れ

後列左から百瀬興政、石川半山
1955(昭和30)年ごろ
木下尚江は1869(明治2)年9月8日、長野県松本の下級武士の家に生まれました。病弱で男友達と遊ぶことは少なく、家の中で絵本を読んだり、大人から世間話や宗教関係の話を聞いたりして過ごしました。また、祖母に連れられ宝栄寺の演説会によく出向き、そこで初めて自由民権運動に接します。
開智学校を経て1881(明治14)年松本中学に入学。万国史の授業で、英国王を倒したピューリタン革命の中心人物 クロムウェルのことを知り、「我心は寝ても醒めても一謎語に注中されている『革命!』」(木下尚江『懺悔』)と感慨を覚えます。以後、木下は学校で「クロムウェルの木下」と呼ばれるようになり、その噂は下級生 相馬愛蔵(後の中村屋の創業者)の耳にまで届きました。
そして、まだ憲法も国会もない1886(明治19)年、"国王を裁く法律"(日本にとって新たな法律の概念)を学ぶため上京、英国憲法の授業がある東京専門学校(現早稲田大学)に入学します。しかし英国憲法が国王の絶対性を根本においているものだと知り、絶望を味わいました。
キリスト教社会主義に目覚める
1888(明治21)年、故郷にもどり信陽日報の記者になります。「新鋭木下尚江入りて紙面更新、一段の生気を放てる」(『松本市史』)と評され、特に県庁移転問題での活躍はめざましく、20歳の若さで地方政治の舞台に登場しました。しかし抵抗にあい、瞬く間に失速。1890(明治23)年、信陽日報は廃刊となってしまいます。
絶望の中、木下はキリスト教に出合い、廃娼運動、禁酒運動などに専念。愛蔵らが創設した東穂高禁酒会では応援演説を行うなど積極的に活動します。一方、生活の道を見出すため1893(明治26)年に代言人(今でいう弁護士)となり、それがきっかけで「信府日報」の主筆をすることに。新聞こそは最も得意な仕事と感じていた彼にとって、この仕事は代言人以上に重要なものでした。
そして1895(明治28)年、三国干渉に対する遼東還付反対運動で共闘した石川半山の後を継ぎ、「信濃日報」の主筆を務めるようになります。
一方で木下は小説家としても幾つか作品を残しています。その一作『霊か肉か』では相馬夫妻や井口喜源治も名を変え登場しています。また演説がうまく「冴えた腕である。練った上にも練らなければ出来ない芸当である」(青木得三『雄弁家木下尚江』)と評されています。
その風貌、印象については創業者 相馬黒光がその著書『穂高高原』の中でこう記しています。「顔色蒼白、痩形で、眉宇(びう)の間何となく苦味走り、また神経質らしい、それを太い線で自らおさへてゐる」
ペンで戦う

1897(明治30)年、木下は選挙疑獄事件の容疑で警察につかまり、1898(明治31)年出獄。この事件は彼にとって転機となりました。「一年半の鉄窓生活は、僕の生涯にとって、実に再生の天寵であった」(木下尚江『神・人間・自由』)と後に記しているように、人生の学問をしたと感じたのです。また「謹で之を世界史の祭壇に献じて犠牲となさんの志相定り」(石川半山宛ての書簡)と決心は定まっていましたが、具体的になにをしたらよいかが分かりませんでした。そんな時、毎日新聞で働いていた石川から「うちにこないか」という誘いがあり入社。青年問題、夫人問題、労働者問題をモットーにしていることを聞き、満身の熱を覚えます。そして1899(明治32)年、「世界平和に対する日本国民の責任」と題する論説を執筆し、以後、平和と反国体を唱えます。田中正造の足尾銅山鉱毒事件問題や普通選挙運動に積極的に取り組み、1904(明治37)年の日露戦争では、「人の国を亡ぼすものは、又た人の為に亡ぼさる。是れ因果の必然なり」(毎日新聞明治36年5月11日「戦争人種」より)と主張し、平民新聞の幸徳秋水や堺利彦ら社会主義の同志とともに非戦運動を開始。また反戦小説『火の柱』を毎日新聞に連載し、ペンを武器に戦いました。
自己を見つめる
しかし1905(明治38)年1月に平民新聞が廃刊。9月には平民社が解散。そして翌年には最愛の母を亡くします。絶望の境地に立った木下は毎日新聞を退社し、遊説をやめ、社会党を脱党。1901(明治43)年に岡田虎二郎の岡田式静坐法に入門し、静坐によって自分の心身を立て直すことに精進します。また、当時信仰を失って生きる目標を見出せなくなっていた黒光に岡田式静坐法を紹介しました。黒光はすぐに元気になり、愛蔵や中村屋のアトリエにいた中村彝までもが静坐道場に通うようになります。やがて木下は仏教世界へと足を踏み入れ、晩年はひたすら坐し、経を写し、思索する日々を送りました。1936(昭和11)年11月5日永眠。68歳でした。