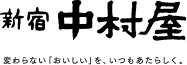純印度式カリー
日本のカレー旨くないな

「東京のカレー・ライス、うまいのないナ。油が悪くてウドン粉ばかりで、胸ムカムカする。~略~カラければカレーと思つてゐるらしいの大變間違ひ。~略~安いカレー・ライスはバタアを使はないでしョ、だからマヅくて食へない」
これは1932(昭和7)年、とある新聞の特集で紹介された、とあるインド人の嘆きです。昭和初期、日本にはすでにカレーライスがありましたが、それはイギリス経由で渡ってきた小麦粉を使った欧風料理。本場インドのカリーとは程遠いものでした。「カラい、アマい、スッパイ、味みなあつて調和のとれたもの一番いい。 舌ざはりカラくなくて、食べたあとカラ味の舌に湧いて來る ものでなくてはダメねェ」。これが本当のカリーなのに・・・。
この、あるインド人とは、インド独立運動で活躍したラス・ビハリ・ボース。すべてはこのインド人と中村屋創業者の出会いから始まりました。
始まりは相馬愛蔵の一言から

ボースは1886(明治19)年、インド ベンガル地方に生まれました。英国の植民地として圧政に苦しんでいた祖国を救おうと、16歳の時親元を離れ独立運動に身を投じます。しかし、インド総督への襲撃をきっかけに、英国政府から懸賞金を懸けられ追われる身となり、1915(大正4)年、日本に亡命します。
一方、日本では、アジア開放運動の志士を守ろうという動きが民間で高まっていました。しかし、日英同盟を結んでいた日本政府は、ボースに国外退去を命じます。このような日本の外交に反発したのが頭山満、犬養毅、寺尾亨、中村弼などそうそうたるメンバーでした。また、中村屋の創業者 相馬愛蔵・黒光夫妻もこれを新聞で承知し、志士の身の上を気の毒に思っていました。そしてある日、店に立ち寄った中村に、愛蔵は「店の裏の洋館なら彼をかくまえるかもしれない」ともらします。この一言が頭山に伝わり、中村屋のアトリエでボースをかくまうこととなったのです。
ボースを陰から支えた俊子

その後ボースは3カ月半中村屋のアトリエで過ごします。中村屋には外国人をかくまうのに都合の良い条件がそろっていました。部屋がたくさんある、人の出入りが多い、外国人の姿も珍しくない、黒光が英語を話せるなど。しかし何よりも大きかったのが、家中の人みんなの心がボースをかくまうことで一致していたことでした。中でも大きな存在だったのが相馬夫妻の娘 俊子。ボースは1916(大正5)年3月に中村屋を出て逃亡生活を続けますが、その連絡役を務めたのが俊子でした。2人は後に結婚し、ボースは相馬家とのつながりを更に深めました。
1919(大正8)年、第一次世界大戦後のパリ講和会議により英国の追及が終了し、ついにボースは自由の身となります。ボースは、翌年には日本に帰化、また中村屋の役員を務めるようになります。しかし平和な日々は長くは続きませんでした。1925(大正14)年、逃亡生活の心労がたたり、俊子が亡くなってしまいます。26歳の若さでした。自分を支えてくれた人を幸せにできなかった・・・。ボースの無念は計り知れないものだったに違いありません。
純印度式カリーの誕生 <1927(昭和2)年6月12日>

大正末、百貨店の新宿進出に中村屋は少なからず脅威を感じていました。また、お客さまから「買い物の時一休みできる場所を設けてほしい」とのご要望を以前からいただいていました。そこで愛蔵は喫茶の開設を検討。しかし喫茶のようなていねいなお客扱いは容易にはできないだろうと尻込みしてしまいます。ボースは祖国インドの味を伝えるため、「喫茶部を作るならインドカリーをメニューに加えよう」と提案しました。そして1927(昭和2)年6月12日、喫茶部(レストラン)を開設。同時に、純印度式カリーが発売されました。

冒頭にもあるように、当時日本に広まっていたのは小麦粉を使った欧風タイプのカレーです。ところが、ボースが作ったのは本場インドのカリー。お米はインディカ米を使用し、スパイスの強烈な香りが漂います。またお肉も日本人が見慣れない骨付きのゴロっとした大きな鶏肉。その異国の料理に日本人は初め戸惑いを隠せませんでした。そこで相馬夫妻はお米をインディカ米のようにソースが浸透し、なおかつジャポニカ米のようにモチモチ感がある白目米にします。しばらくするとお客さまが骨付き肉やスパイスの香りにも慣れ、次第に売り上げが伸びていくようになりました。当時、町の洋食屋のカレーが10銭から12銭程度でしたが、中村屋のカリーは80銭。それにも関わらず飛ぶように売れたそうです。
こうして、純印度式カリーは中村屋の名物料理になりました。そこにはボースの、相馬家との出会いと、祖国に対する愛情があったのです。