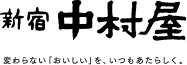高村光太郎たかむら こうたろう
詩人ではなく彫刻家

高村光太郎といえば『智恵子抄』『道程』などの詩が教科書に掲載されるほど有名で、詩人のイメージがあります。しかし、その本質は彫刻家であり、詩の作成は彫刻から文学的なものを排し、造型の理想を追い求めるためになされました。光太郎が自身を「宿命的な彫刻家」と呼ぶように、そこまで彫刻に執着する背景には、偉大な彫刻家である父との確執がありました。
幼年、青年期
1883(明治16)年、高村光太郎(本名 みつたろう)は父 光蔵(光雲)、母 わかの長男として現在の東京都台東区で生まれました。父は仏師であり、明治・大正時代を代表する彫刻家でしたが、帝室技芸員として、また東京美術学校の教授として体制側にいる古いタイプの芸術家であり、光太郎が志したオーギュスト・ロダンに代表される新たな芸術の対極にありました。このことが一つの原因となり、光太郎は父に対して鬱積したものを持ち続けるようになります。
光太郎は5~6歳のころから、父にもらった小刀で彫刻のまねごとを始め、15歳のとき、父が教壇に立つ東京美術学校予備の課程に進みました。翌年には本科へ進み、彫刻の道を目指すことを本格的に決意。しかし、彫刻の道を選んだことで、その道の先達としての父への負い目、抵抗を終生ひきずることになります。1902(明治35)年、20歳で同校を卒業し、その2年後、ロダンの彫刻「考える人」の写真を見て衝撃を受けた光太郎は、父への反発も含めて傾倒。この傾倒ぶりはカミイユ・モオクレエルの『オオギュスト・ロダン』(英語版)を入手し、「私は寝てもさめても手離さなかった。相当に詳しい此の伝記書を実に熱心に読んだ。食べるように読んだとは此の時の事であろう」(『ロダンの手記談話録』婦人公論36巻11号)というほどのものでした。ちょうどこのころ、荻原守衛(碌山)も彼の地、フランスでロダンの「考える人」の実物を見て感激、本格的に彫刻の世界で生きていく決意を固めています。
碌山との出会い

日本でのロダンの紹介が“日本の彫刻が近代の扉を開くカギとなった”といえます。そしてこのカギは碌山と光太郎の2人によってもたらされたと考えられています。碌山は主に自らの作品から、光太郎はもっぱら文筆活動によってロダンを追求しました。共にロダンから受けた感銘は大きく、そのことは2人の残された書簡、日記などから充分伺い知ることができます。
光太郎は1906(明治39)年、24歳のときに自費で渡米。ニューヨークで柳敬助、碌山と出会います。この年、碌山は渡仏し、光太郎は翌年イギリスに、更に翌々年にはフランスに移り住みます。この外遊で碌山との親交、将来の伴侶となる智恵子との縁を結ぶ柳との出会いを得たのでした。1909(明治42)年に帰国後、光太郎は碌山との縁で中村屋にも出入りし、碌山との仲はより一層深いものになっていきます。そして翌年、光太郎は日本で初の画廊琅かん洞を開き、自分の作品をはじめ碌山や柳、斉藤与里の作品を展示。経営は失敗しますが新たな試みとして評価されます。この年碌山が亡くなり、関西旅行中の光太郎はすぐに帰京、その死を悼みました。
「荻原守衛」の題名で光太郎は詩をよみ、また後年「荻原守衛の首」(未完)と題した彫刻にとりかかりました。
智恵子との出会い
芸術論を文筆で戦わせたことも有名で『スバル』に掲載された1910(明治43)年発行の『緑の太陽』は新しい時代の芸術の潮流の一つとなりました。柳の夫人、八重の紹介で女性雑誌『青鞜(せいとう)』の表紙絵を描いていた長沼智恵子と出会い、1914(大正3)年、33歳のとき、光太郎は彼女と生活を共にします。ちょうどこの年、最初の詩集『道程』を出版、詩の世界でも頭角を表します。
智恵子は1938(昭和13)年53歳で没しますが、その半生は精神病と肺結核との戦いでした。有名な『智恵子抄』は3年後の1941(昭和16)年発行されました。
高村光太郎は1956(昭和31)年4月2日、愛してやまなかった智恵子と同じ墓に眠ることになりました。